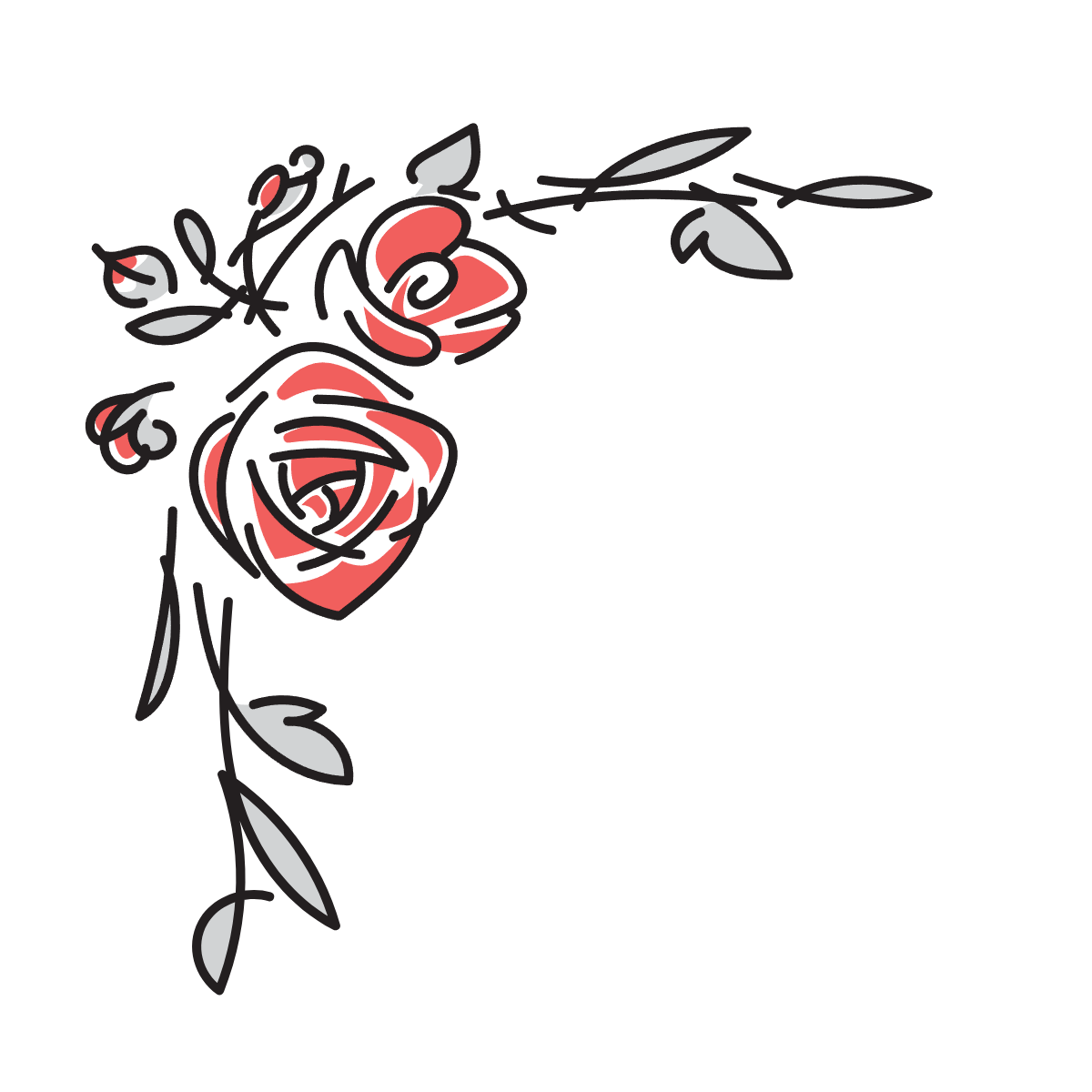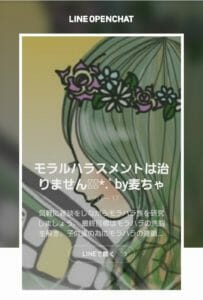DV加害を前提とした危険な状況下、安全を確保するために、保護命令という制度があります。
これは相手方の行動を制限できるもので、発令されることとなれば、とても強い効力とともに安心を得ることが出来ます。
5種類の保護命令があります。
(2)申立人への電話等禁止命令
(3)申立人の子への接近禁止命令
(4)申立人の親族等への接近禁止命令
(5)退去命令
基本的に(1)の本人への接近禁止とセットで他の命令をオプションでつけます。
申請用紙を貰うには、予め相談履歴が必要になりますので、一般的にはいきなり出向いて手に入れられるものではありません。
万が一、事前にどこにも相談をしていなかった場合は、公証役場で「公証人面前宣誓供述書」という書類を作成する必要があります。
公証人の面前で、その書面の内容が真実であることを宣誓し作成するのです。
こちらは公証役場にて費用がかかってしまうことを考えておく必要がありますが、公的機関での相談履歴がないならば、この宣誓供述書を保護命令の申立書に添付しなければ保護命令は発令されません。
地裁での申し立ては、本人もしくは弁護士などの代理人のみが行えます。(申し立て本人は内縁関係でも可能)
弁護士を依頼しているならば弁護士費用が必要ですので、費用をかけたくないならば自分で地裁に申し立てすると、2,000円台で申し立て完了です。
申し立てをする裁判所は、相手方の居住地の管轄裁判所になります。
申し立て後、申立人もしくは代理人弁護士に面接(審尋)が裁判所で行われ、それにより2週間ほどで保護命令発令か、否かが定められます。
必ずしも認められるとは限りませんので、確実な証拠や相談履歴が必要なのだと思われます。
ここでいう暴力とは、身体的暴力だけでなく、生命を脅かす脅迫(精神的暴力)なども含まれますが、やはり精神的暴力に関しては、証拠などが不十分だと却下の対象になりうるでしょう。
精神的暴力の参考としては、モノが壊れていることが多い、暴言は「死ね」「殺すぞ」などが基準となり、画像、録音、メールなど、何らかの証拠が必要になります。
証拠不十分で却下されそうになったら、裁判所から『このままだと却下される』と連絡が来るらしく、離婚調停をこの先に控えている場合は、保護命令申し立てを取り下げることが最善の策になると聞きました。
裁判所が保護命令申請を却下した記録が残ると、不利になるかもしれないという懸念からです。
また保護命令を出すということを、事前に相手方へ伝えることは避けましょう。
そのような知識を与えてしまうと、警察などへ先回りし、『自分が暴力被害にあっている』等の虚言はもちろん、被害者を演じる加害者は珍しくないからです。
何においても自分から予告することはやめて、保護命令申請は黙って申し立てることが重要です。
保護命令に違反したら1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられますので、これで少しは大人しくなるかもしれないという期待を込めて。